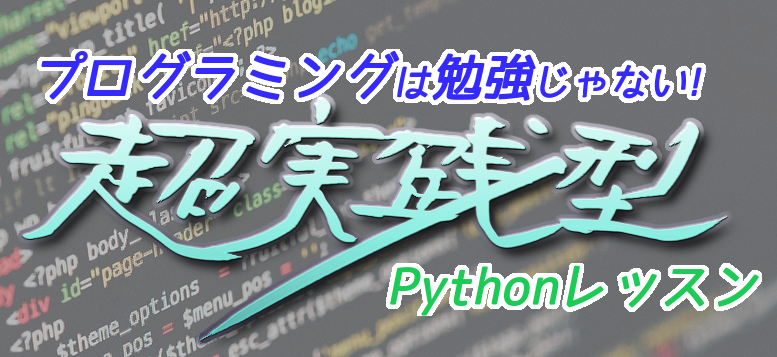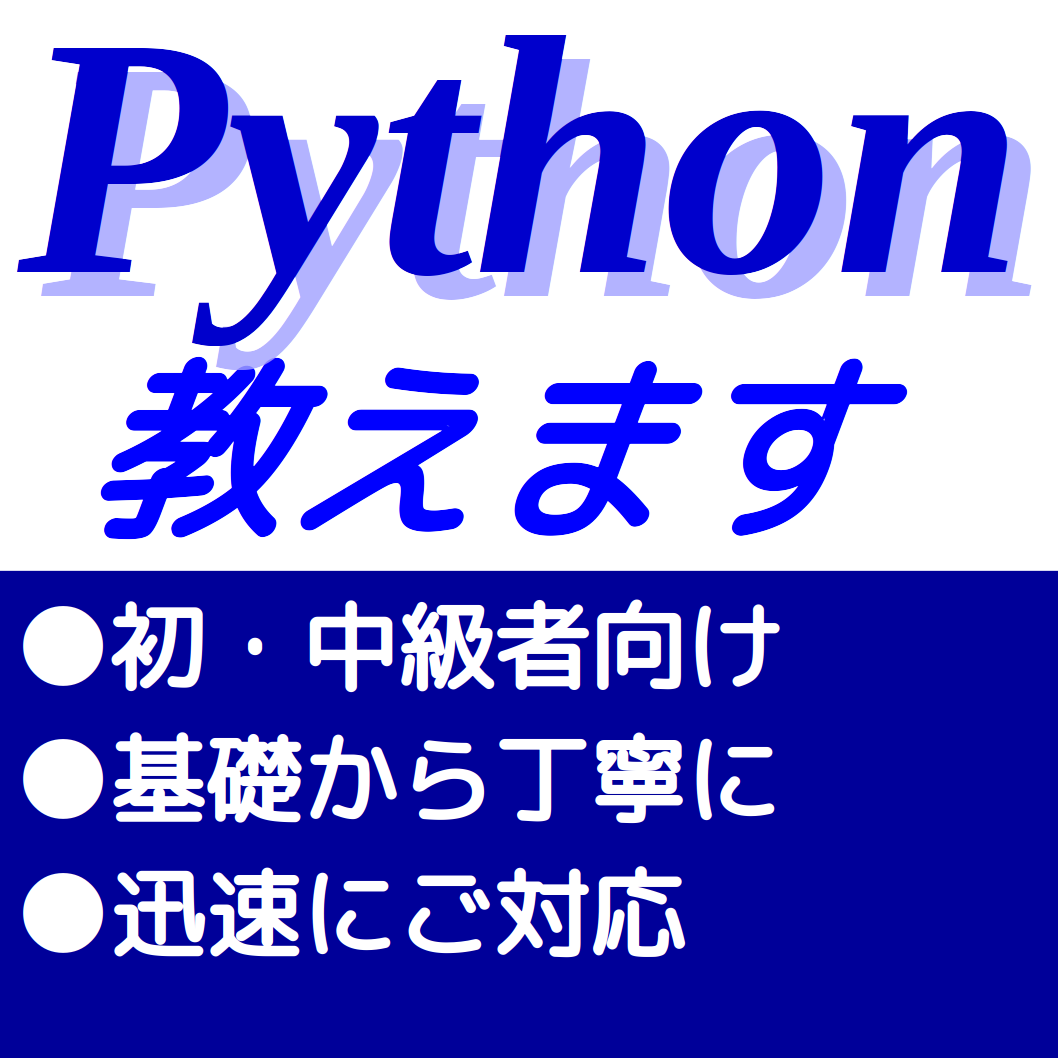大西さんISS船長就任:宇宙への貢献を可視化するPythonスクリプトと共に
「貢献の証、全力で頑張る」―― 宇宙飛行士の大西卓哉さんが国際宇宙ステーション(ISS)の船長に就任されました。これは日本人として3人目の快挙であり、日本の宇宙開発における大きな一歩と言えるでしょう。
大西さんの船長就任は、長年の努力と卓越した能力が認められた結果であり、私たちに大きな感動と勇気を与えてくれます。宇宙という極限状態での任務遂行、そして国際的なチームを率いるリーダーシップは、まさに「貢献の証」そのものです。
宇宙への貢献は、目に見えにくい部分も多くあります。そこで、今回は大西さんのISS船長就任を記念して、宇宙への貢献をイメージし、可視化するためのPythonスクリプトを作成してみました。
このスクリプトは、指定した期間におけるISSの地球周回数を計算し、その距離を可視化するものです。ISSがどれだけの距離を移動し、地球を周回しているかを具体的な数値として示すことで、宇宙での活動のスケールを少しでも感じていただければと思います。
以下が、Pythonスクリプトになります。
import math
def calculate_orbit_distance(orbit_radius, num_orbits):
circumference = 2 * math.pi * orbit_radius
total_distance = circumference * num_orbits
return total_distance
def main():
iss_orbit_radius = 6771 # 地球半径(6371km) + ISSの高度(400km)
num_orbits = 17 # 1日の周回数 (約16周だが、計算しやすいよう17周とする)
days = 30 # 計算期間 (日数)
total_orbits = num_orbits * days
total_distance = calculate_orbit_distance(iss_orbit_radius, total_orbits)
print(f"ISSは{days}日間で約{total_orbits}周回します。")
print(f"総移動距離は約{total_distance:,.0f} kmです。") # 数値を見やすくカンマ区切りにする
if __name__ == "__main__":
main()
このスクリプトを実行すると、ISSが30日間で約510周回し、総移動距離は約21,572,720kmにも及ぶことがわかります。これは地球539周分に相当する距離です。
この数値を通して、ISSでの活動がいかにダイナミックで、地球規模での影響力を持っているかを再認識することができます。
大西さんの船長就任は、日本の宇宙開発の未来を照らす灯台のような存在です。このPythonスクリプトが、少しでも宇宙への興味関心を深め、宇宙開発への貢献を考えるきっかけになれば幸いです。大西さんの今後の活躍を心から応援しています。
科学ニュース一覧に戻る