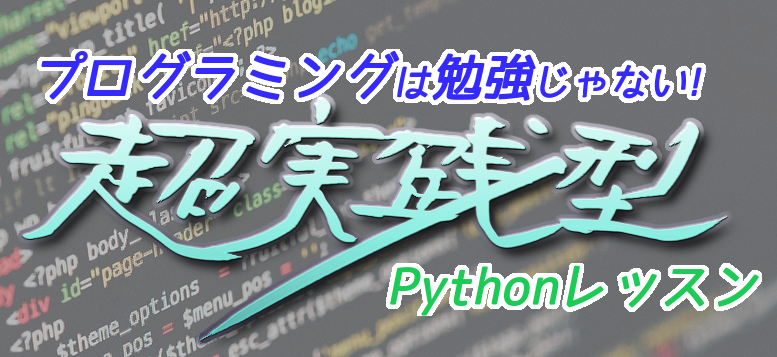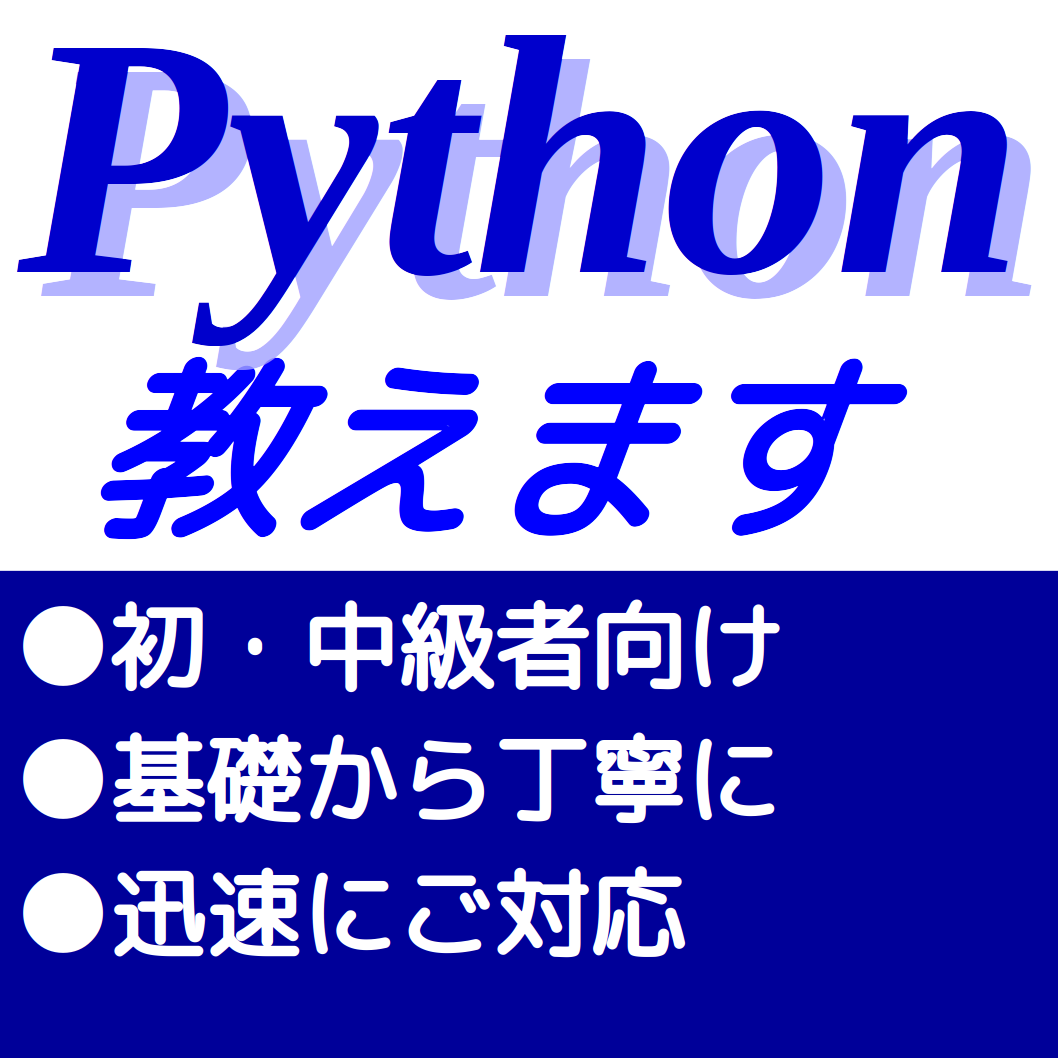身近な数理とPythonの出会い:一家に一枚ポスターから広がる世界
科学技術週間、皆さんは何か新しい発見はありましたか? 今年も魅力的な企画が盛りだくさんでしたが、特に注目を集めたのは、科学技術振興機構(JST)が作成した「一家に1枚ポスター」の新作です。今回のテーマは「数理」。普段意識することは少ないかもしれませんが、数理は私たちの生活のあらゆる場面に潜んでいます。
例えば、スマートフォンの検索エンジンは複雑なアルゴリズムによって瞬時に情報を探し出しますし、天気予報は過去のデータに基づいて未来を予測する数理モデルの結果を表示しています。交通機関の運行計画、金融商品の価格変動、感染症の流行予測、そしてゲームのキャラクターの動きまで、数理は社会を支える基盤となっているのです。
「難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、数理は意外と身近なところに顔を出します。ポスターでは、そんな数理の魅力をわかりやすく、親しみやすいイラストとともに紹介しています。家族みんなで数理の世界に触れる良い機会になるでしょう。
さて、数理の世界をより深く理解するために、今回はPythonを使って簡単なスクリプトを作成してみましょう。テーマは「フィボナッチ数列」。これは、前の2つの数を足し合わせて次の数を作る数列で、自然界の様々な場所(花びらの数、植物の葉の付き方、貝殻の螺旋など)に見られる美しいパターンです。
以下に、フィボナッチ数列の最初のn個の項を生成するPythonスクリプトを示します。
def fibonacci_sequence(n):
list_fib = [0, 1]
while len(list_fib) < n:
next_fib = list_fib[-1] + list_fib[-2]
list_fib.append(next_fib)
return list_fib
def main():
n = int(input("フィボナッチ数列の項数を入力してください: "))
fib_sequence = fibonacci_sequence(n)
print("フィボナッチ数列:", fib_sequence)
if __name__ == "__main__":
main()
このスクリプトを実行すると、ユーザーが指定した数のフィボナッチ数列の項が表示されます。たった数行のコードで、自然界に隠された数理の美しさを垣間見ることができるのです。
このコードはあくまで入門編。Pythonは、より複雑な数理モデルを構築したり、大量のデータを解析したりするのに役立つ強力なツールです。例えば、機械学習のライブラリを使えば、過去のデータから未来を予測するモデルを自分で作成することもできます。
今回の「一家に1枚ポスター」をきっかけに、数理の世界への興味を持たれた方は、ぜひPythonなどのプログラミング言語に挑戦してみてください。きっと、新たな発見と創造の喜びが待っているはずです。科学技術週間は終わりましたが、数理の世界への探求はこれから始まるのです。
科学ニュース一覧に戻る